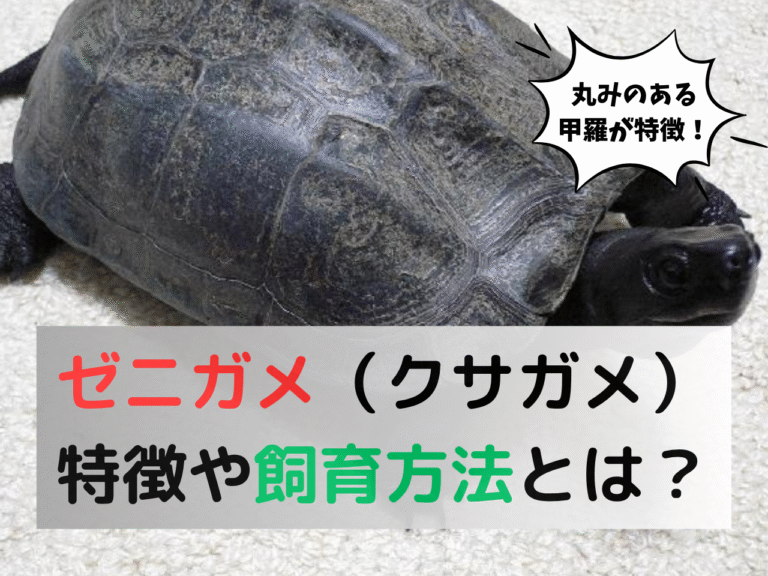ゼニガメは日本で古くから親しまれている水生カメで、その可愛らしい見た目と飼いやすさから、初めて爬虫類を飼う人にも人気があります。
特にクサガメの幼体は「ゼニガメ」と呼ばれ、ペットショップやホームセンターなどでも手軽に購入できます。
この記事では、ゼニガメの基本的な特徴や選び方から、健康的に育てるための飼育方法まで、わかりやすく解説します。
ゼニガメってどんなカメ?
もともと「ゼニガメ」という言葉はニホンイシガメの幼体を指していましたが、現在では主にクサガメの赤ちゃんをゼニガメと呼ぶのが一般的です。
丸みのある甲羅の形が、昔の硬貨「銭」に似ていることから、その名がつけられました。ゼニガメは小さいときは500円玉ほどのサイズですが、大人になると甲長20〜30cmにもなります。
見た目の可愛さだけで飼い始めると、のちのち水槽が手狭になったり、お世話が大変になったりすることがあるので、成長後の姿もイメージして準備しましょう。
健康なゼニガメを選ぶためには、甲羅に白いカビや変色がないか、目がしっかり開いていて腫れていないか、元気に泳いでいるかどうかなどをよく観察することが大切です。皮膚や甲羅に傷がある個体は避けるようにしましょう。
ゼニガメの飼育に必要な基本セット
ゼニガメの飼い方にはいくつかの基本アイテムが必要です。幼体なら30cm程度の水槽でも始められますが、将来的には60〜90cmの広めの水槽が理想です。
また、ゼニガメは意外と力が強く、水槽から脱走することもあるため、フタは必須です。他にも、水温を一定に保つための水中ヒーターや水温計、紫外線ライトとバスキングライト、甲羅干し用の陸地スペース、ろ過装置(フィルター)、そしてカメ専用のフードも揃えておきましょう。
最初から成長を見越して設備を整えておくことで、後々の手間や費用を減らすことができます。
ゼニガメの水換え頻度と水質管理
ゼニガメは水の中で多くの時間を過ごすため、水質が健康に直結します。水が汚れると甲羅のトラブルや皮膚炎、病気の原因になってしまうことも。
水換えの目安としては、週に2回、できれば毎日1/3程度の水を部分的に入れ替えるのが理想です。ろ過装置(フィルター)を使うと、汚れを減らし水質を安定させやすくなります。
水温は26〜28℃が適温で、これより低いと活動量が落ちたり、食欲がなくなったりすることもあります。特にベビーの時期は水温が低いと成長に悪影響を与えるため、冬場は必ずヒーターを使って10℃以下にならないように注意しましょう。
甲羅が白く濁る、皮膚が赤くなるといった異常は水質悪化のサインです。水換え習慣とフィルターの併用で、きれいな水を保つことが長寿の秘訣です。
陸地と甲羅干しの大切さ
水の中で生活しているイメージの強いゼニガメですが、実は「甲羅干し」がとても大切です。甲羅をしっかり乾かすことで、カビや病気を予防し、健康を維持することができます。
甲羅干し用の陸地には、安定感のある素材(流木や人工の島など)を使い、体全体が乾かせるようにします。そこにバスキングライトと紫外線ライト(UVB)を設置して、1日に1時間以上の日光浴をさせましょう。
紫外線ライトは、ビタミンD3を体内で作るために必要で、カルシウムの吸収にも大きく関わっています。窓際の日差しだけでは不十分なことが多いため、屋内飼育ではライトの導入がとても重要です。

出典:Wikipedia
ゼニガメのエサと給餌のコツ
ゼニガメは雑食性で、野生では昆虫や魚、水草などを食べています。飼育下では、栄養バランスの取れたカメ用フードを主食とし、安心して与えられる市販品を選ぶのが基本です。
ベビー期は1日2〜3回、小さく砕いた餌を与えます。成長とともに1日1回、または2日に1回と頻度を減らしていきましょう。食べ残しは水を汚す原因になるので、すぐに取り除いて部分的に水換えすることが大切です。
変化をつけるために、小エビ(クリル)や刻んだ野菜、ササミなどをたまに与えると、食欲も維持しやすくなります。
ゼニガメが急に餌を食べなくなった時は、水温の変化や環境の変化が原因のことも多いです。焦らずに水温や照明、レイアウトを見直してみましょう。
単独飼育が基本!混泳の注意点
ゼニガメは縄張り意識が強いため、基本的には1匹ずつの単独飼育が安心です。複数で飼うと、体格差によるいじめやエサの奪い合いが起こり、どちらかがストレスを感じたり、栄養不足になったりすることがあります。
また、魚やエビと一緒に飼うと、ゼニガメが捕食してしまうケースも少なくありません。混泳させたい場合は、広い水槽を用意して、仕切りなどで物理的に隔てるなどの工夫が必要です。
冬眠は初心者NG!ヒーターで保温を
自然界のゼニガメは冬になると冬眠しますが、飼育下での冬眠は非常にデリケートで、失敗すると命に関わることもあります。
特に初心者のうちは、ゼニガメを冬眠させずに冬でも活動させる「非冬眠飼育」をおすすめします。
冬場は必ずヒーターで水温を保ち、特にベビーのゼニガメは低温に弱いため、10℃以下にならないよう注意しましょう。
ゼニガメの健康チェックと長生きのコツ
ゼニガメは毎日の観察と適切な環境があれば、20年以上も生きることができます。健康チェックとしては、甲羅の色や形に異常がないか、目や鼻に分泌物や腫れがないか、食欲があるか、泳ぎ方が普段通りかをよく観察することが大切です。
特に注意したいのは、ビタミンA不足による目の腫れや、甲羅の変色・変形です。少しでも異変を感じたら、爬虫類の診察ができる動物病院に早めに相談しましょう。
まとめ
ゼニガメの飼育は、見た目の可愛さだけで始めると意外と奥が深いものです。水質や水温の管理、日光浴の確保、そして食事のバランスなど、毎日のケアを丁寧に行うことが大切です。
最初から広めの水槽や必要な機材を揃えておけば、成長後も安心して飼い続けることができます。単独飼育を基本とし、冬はヒーターで保温、餌は成長に合わせて調整することで、ゼニガメは健康に長生きしてくれるでしょう。
愛情を込めてお世話すれば、ゼニガメは20年以上を一緒に過ごせる大切なパートナーになります。最後までお読みいただきありがとうございました☺