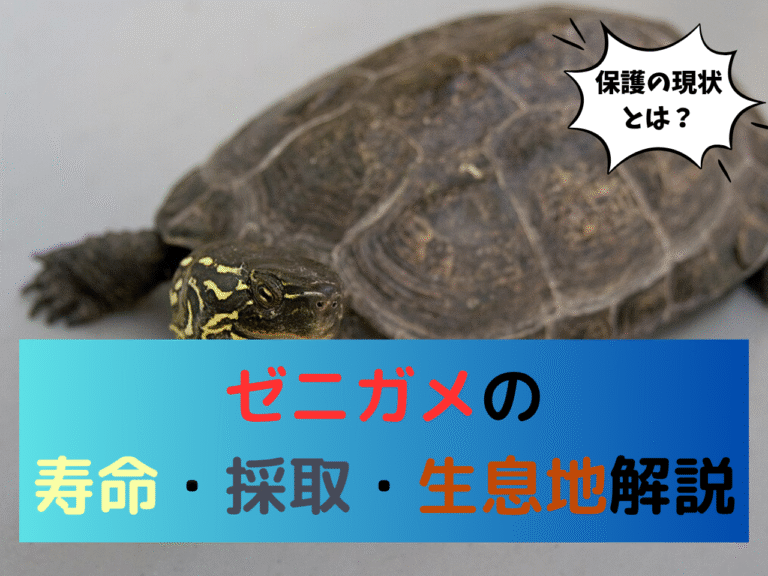ゼニガメは、日本の淡水域で昔から親しまれてきたカメで、ペットとしても非常に人気があります。その小さな体と愛らしい仕草は多くの人を魅了してきました。
この記事では、野生下での現状と保護の取り組みまで解説していきます。これから飼育を考えている方や、自然観察に興味のある方に向けて、ちょっとしたアドバイスも交えながらお伝えしていきます。
ゼニガメとは?
ゼニガメという名前は、かつては日本固有種であるイシガメの幼体に使われていましたが、現在では主にクサガメの幼体を指す呼び方として定着しています。
とくにオスは甲長が15〜17センチほどで成長が止まりますが、メスはそれ以上に大きくなり、体重が2キロに達することもあります。
ゼニガメは泳ぐのがあまり得意ではなく、流れのゆるやかな川や池、沼地、水たまり、水田など、静かな水辺を好んで暮らしています。
ふだんは昼間に活動しますが、夏の暑い時期には朝夕や夜に動くことが多くなる子もいます。おひさまの光を浴びるのが好きで、日光浴を楽しむ様子もよく見られます。また、陸を歩いて別の水辺に移動することもあります。
ゼニガメは小さいうちが可愛いですが、成長後のサイズも考えて水槽の大きさや飼育環境を計画することが大切です。将来を見据えた準備が、長く元気に育てるコツになります。
ゼニガメの寿命
ゼニガメの寿命は非常に長く、飼育環境が整っていれば20〜30年ほど生きるのが一般的です。飼い主さんの管理が行き届いていれば、40年以上生きる個体も珍しくありません。
中には100年近く生きたという記録もあるほどで、まさに“生涯のパートナー”として迎える覚悟が求められます。
ゼニガメを長生きさせるためには、水槽の水を常に清潔に保つことが大切です。特にフンや食べ残しはすぐに水質を悪化させてしまうため、こまめな掃除が欠かせません。
また、食事にも工夫が必要で、カルシウムやビタミンをしっかり摂れるよう、バランスの良い配合飼料に加えて時折、小魚や乾燥エビ、野菜なども取り入れると良いでしょう。
紫外線ライトや日光浴を取り入れることで、甲羅や骨の健康を保ちやすくなります。水温管理も忘れずに。夏は暑くなりすぎないように、冬は20度以上を保てるよう工夫してあげると、快適に過ごせます。
ゼニガメの長寿の秘訣
ゼニガメはとても繊細で、実はストレスに弱い生きものです。なでたり、頻繁に触れたりすると驚いてしまうこともあり、静かで落ち着ける環境が大切です。
周囲が騒がしかったり、夜遅くまで明るかったり、隠れる場所がなかったりすると、安心して過ごせなくなります。
また、水が汚れていたり、狭い水槽で思うように動けなかったりするのも、カメにとってはストレスになります。水温や気温が合っていない、近くに他の動物がいるなど、ちょっとしたことでも影響を受けてしまうのです。
そんなゼニガメが快適に暮らせるようにするには、なるべくそっと見守りながら、静かで落ち着ける場所に水槽を置き、水を清潔に保つことが大切です。
ときには水槽の外でのんびりお散歩させてあげたり、隠れ家を用意して安心できる場所を作ってあげたりしましょう。季節や室温に合わせて温度調整も忘れずに。
他のペットや刺激になるものは近づけないようにし、特に繁殖期は静かにそっとしておくのがポイントです。
ゼニガメが元気に長生きするためには、ストレスの少ない穏やかな環境を整えてあげることが一番。食欲が落ちたり、じっと隠れていたり、いつもと違う様子が見られたら、環境を見直して安心できる空間
を用意してあげましょう。

出典:Wikipedia
ゼニガメはどこにいるの?
ゼニガメ(クサガメの子ども)は、日本でもよく見かけるカメとして知られていますが、もともとは外国で生まれたカメだということをご存じでしょうか?
本来、ゼニガメは中国の東部から南の方、そして韓国や香港など、東アジアのあたたかい地域に自然に暮らしていました。田んぼや池、小さな川など、水のある場所を好んで住んでいます。
そして、日本には昔から人の手によって持ち込まれ、今では北海道の南西部から本州、四国、九州をはじめ、佐渡島や淡路島、対馬、五島列島、奄美大島、沖縄本島などの島々にも広がって住んでいます。
日本ではゼニガメは“もともとそこにいたカメ”というよりは、“あとからやってきて根づいたカメ”なんです。
また、台湾でも人の手によって持ち込まれ、今では野生化して定着していることがわかっています。ゼニガメがいろいろな場所に住める理由は、水辺の環境にうまくなじむ力が強く、寒さや暑さにもある程度耐えられる性格だからです。
こういった特徴が、初心者でも飼いやすい理由のひとつになっています。
ゼニガメを自然の中で観察したい場合は、静かな池や水田、石の上で甲羅干ししている姿をそっと探してみましょう。双眼鏡を使えば、近づかなくてもじっくり観察できますよ。
ゼニガメの採取について
自然の中で暮らすゼニガメの数は年々少なくなってきています。その理由には、川や池などの開発による自然の減少、水の汚れ、人の手によるとりすぎ(乱獲)などが関係しています。
とくに海外ではゼニガメが食用や薬用としてもとらえられることがあり、今では韓国や中国、台湾では保護の対象として大切にされています。
日本では一見すると野生のゼニガメが多く見られますが、実はその多くが海外から入ってきたカメであったり、もともと日本にいたニホンイシガメと交雑している可能性もあります。
こうした背景から、ゼニガメを自然の中から捕まえて飼うことは、現在ではおすすめできません。特に野生のカメたちは、環境の変化やストレスにとても敏感です。
むやみに触れたり持ち帰ったりすると、命を縮めてしまうことにもつながります。現在、ペットショップなどでは、飼育用に養殖されたゼニガメが販売されています。
これらは自然環境に負担をかけずに飼えるように育てられたものなので、飼いたい場合はこのような流通経路を選ぶことが大切です。
また、一部では「キンセンガメ」や「ウンキュウ(ニホンイシガメとの雑種)」といった名前で販売されていることもありますが、こうしたカメたちも丁寧に育ててあげる必要があります。
ゼニガメは自然のまま観察するのが一番です。飼育を考える場合は、正規の販売ルートで迎え入れ、最後まで責任を持って育てましょう。
まとめ
ゼニガメは見た目の可愛らしさから気軽に飼われがちですが、実際には20年〜30年、時にはそれ以上も生きる、とても長寿な生き物です。
成長すれば体も大きくなり、飼育には広いスペースと適切な環境管理が欠かせません。また、 採取や生息の観点から見ても、自然下のゼニガメは年々その姿を見かけにくくなっており、特に日本固有のイシガメは保護が急務となっています。
野生のゼニガメを見つけた場合は、無理に捕まえたりせず、そっと観察するスタイルで自然とのふれあいを楽しみましょう。
私たち一人ひとりの行動が、ゼニガメの未来を守る第一歩になります。最後までお読みいただきありがとうございました☺