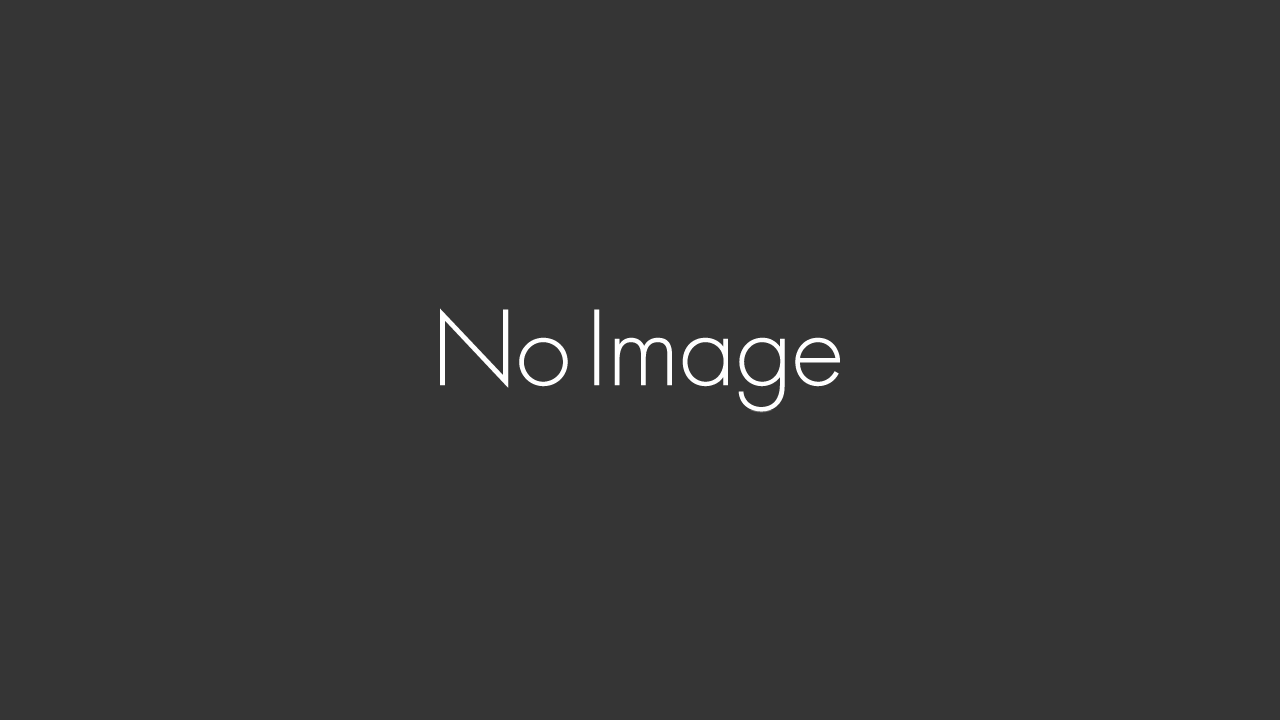ニシアフリカトカゲモドキ(通称ニシアフ)は、その穏やかな性格と飼いやすさから、レオパ(ヒョウモントカゲモドキ)に続く人気種として注目を集めています。
飼育において特に重要となるのが「餌」の選び方と与え方。ニシアフは完全な肉食性であり、適切な食事管理は健康な成長と長寿に直結します。
この記事では、ニシアフのエサについて、初心者でも安心して取り入れられる活餌・冷凍餌・人工餌の使い分けから、給餌のタイミング、管理のコツまでを詳しく解説します。実際の飼育現場で役立つ情報を、専門的な視点を交えてお届けします。
ニシアフの食性と基本的な餌の考え方
ニシアフは完全な昆虫食の夜行性ヤモリであり、自然界ではクモや小型昆虫を中心に捕食します。飼育下でもその性質は変わらず、基本は昆虫ベースの餌が中心となります。
活餌としてはイエコオロギ、フタホシコオロギ、デュビアローチ(アルゼンチンモリゴキブリ)などが主流です。
加えて、管理がしやすく保存も利く人工餌や冷凍餌の選択肢も増えており、ライフスタイルに合わせた給餌が可能になっています。
個体ごとに好みや食いつきに差があるため、最初は複数の餌を用意し、反応を観察しながら調整していくのが成功のポイントです。
ペットショップで購入する際は「人工餌に慣れている個体かどうか」を事前に確認すると、初期の給餌がスムーズになります。
活餌の種類と特徴
ニシアフリカトカゲモドキにとって、活餌は最も自然に近い形で栄養を摂れる理想的な食事です。特に食いつきが良く、成長期や体調管理にも大きく貢献します。
ただし、種類ごとの栄養バランスや管理方法を理解しておかないと、思わぬトラブルにつながることも。ここでは、飼育者に人気の高い活餌の特徴と、それぞれのメリット・注意点を詳しく解説していきます。
1.コオロギ類(イエコオロギ・フタホシコオロギ)
定番中の定番。イエコオロギは小さくて動きが素早く、食欲を刺激しやすい一方、フタホシはやや大きめで動きが緩やか。ニシアフの年齢やサイズに応じて使い分けが可能です。
管理のコツ: 昆虫ゼリーや野菜で栄養補給(=ガットローディング)を行い、卵パックなどで隠れ家を作ることで共食い防止になります。
2.デュビアローチ
脂肪・タンパク質ともにバランスが良く、消化にも優れているため、メイン餌として重宝されます。動きがゆっくりなのでニシアフも食べやすく、飼育者にとっても扱いやすいのが特長。
注意点は脱走防止の徹底。繁殖力が強く、一度逃げると家中に広がる恐れがあります。密閉型ケースで管理しましょう。
3.ミルワーム・ハニーワーム・シルクワーム
嗜好性が高く、拒食時などの「補助餌」として最適。ただし脂肪分が多いため、主食として与えるのはNG。週1〜2回までの頻度が理想です。
与える際は、頭部を潰してから与えると誤嚥や消化不良の予防になります。
人工餌のメリットと注意点
人工餌は、「活餌の管理が面倒」「虫が苦手」という飼育者にとって便利な選択肢です。現在はニシアフにも使えるレオパ用のフードが多く市販されており、主食としても利用可能です。
主な人工餌の種類
- レオパドライ(乾燥ペレット):水にふやかしてから使用。保存性が高くストックに便利。
- レオバイト(粉末タイプ):コオロギ由来の高嗜好性フード。必要に応じてカルシウムを添加。
- グラブパイ(ゼリー状):アメリカミズアブを原料にした高栄養フード。お湯で溶かして固めて使用。
個体によってはすぐには食べないこともありますが、活餌に混ぜて徐々に慣らすブレンド給餌が効果的です。
人工餌は長期的に安定した栄養管理が可能です。最初はピンセットで口元に運び、活餌と一緒に与えることで、自然な移行が可能になります。

出典:Wikipedia
冷凍餌をあたえてみよう
「虫を触るのがどうしても苦手……でもニシアフの健康には妥協したくない」という飼育者にとって、冷凍餌(フローズンインセクト)はベストチョイスです。
保存が効きやすく、常温の活餌に比べて匂いも少ないため、室内での管理がしやすく衛生面でも安心できます。
使用時には、与える直前にぬるま湯で10分ほどしっかり解凍し、栄養補助としてカルシウムパウダーをまぶすのが基本です。
生餌に比べてニシアフの反応がやや鈍くなることもありますが、ピンセットで軽く揺らしたり、トントンと動きをつけたりすることで、狩猟本能を刺激し、食いつきが改善されやすくなります。
冷凍餌は「活餌が苦手」「手間を減らしたい」といった飼育者にとっての味方であると同時に、飼育スタイルに合わせた柔軟な栄養管理を可能にしてくれる存在です。
給餌の頻度と時間帯
ニシアフの年齢や活動量によって、給餌の回数と量を調整する必要があります。
| 年齢 | 頻度 | 目安の量 |
| 幼体(〜6ヶ月) | 毎日 | 2〜3匹程度 |
| 亜成体(6〜12ヶ月) | 2日に1回 | 5〜7匹 |
| 成体(1年以上) | 週2〜3回 | 7〜10匹 |
| 高齢個体 | 週1〜2回 | 体調を見て調整 |
ベストな給餌時間帯は夜間から明け方にかけて。ニシアフは夜行性のため、暗くなってからの活動が活発です。
拒食・体調不良への対応
ニシアフリカトカゲモドキ(通称ニシアフ)が急に餌を食べなくなった場合、多くの飼育者が不安になるかと思います。しかし、焦らず落ち着いて、まずは以下のポイントを一つひとつチェックしてみましょう。
まず確認したいのが温度管理です。ケージ内の温度が低すぎると、ニシアフは体がうまく動かず、代謝が落ちてしまいます。その結果、活動量が減り、食欲も失われていきます。
理想的な飼育温度は日中で28〜30℃ほど。夜間に若干下がっても問題ありませんが、急激な温度差は避けるようにしましょう。とくに冬場やクーラーの効いた室内ではヒーターやサーモスタットの見直しが必要になることもあります。
次に見直したいのが湿度管理。湿度が不足していると、脱皮不全や尿酸の排出トラブルにつながり、それが体調不良や拒食の原因になることがあります。
ケージ内の一部に湿度の高い「シェルターゾーン」を設けるなど、メリハリのある環境づくりを意識すると、ニシアフにとっても快適になります。
また、餌のサイズも見落としがちなポイントです。とくに幼体や小柄な個体に対して大きすぎる餌を与えてしまうと、飲み込むのに苦労するだけでなく、消化不良や嘔吐のリスクも出てきます。
餌のサイズは「頭の幅以下」を基本に選ぶと安全です。
数日以上の拒食が続いたら、ハニーワームやグラブパイなど嗜好性の高い餌で再度チャレンジ。それでも改善しない場合は爬虫類専門の動物病院へ相談を。
餌の保存と衛生管理
飼育者にとって餌の管理は健康維持の要でもあります。以下の点に注意しましょう。
- 活餌:週2〜3回の餌交換、ケース清掃、卵パックの交換
- 人工餌:直射日光を避け、冷蔵庫保管。開封後は1か月以内に使い切る
- 冷凍餌:再冷凍は避け、解凍後12時間以内に与える
清潔な環境を保つことで、雑菌繁殖やカビによる病気リスクを大幅に軽減できます。
まとめ
ニシアフリカトカゲモドキにとって、餌は単なる栄養補給だけではなく、健康を支えるライフラインです。活餌・冷凍餌・人工餌のそれぞれに利点と注意点があり、大切なのは「自分の飼育スタイル」と「個体の好み」に合ったバランスを見つけること。
活餌で本来の狩猟本能を刺激しつつ、人工餌や冷凍餌で管理の手間を減らすなど、柔軟な組み合わせを取り入れることで、ニシアフとの暮らしはより快適になります。
日々の観察とちょっとした工夫で、ニシアフの健康状態は大きく変わります。これから飼育を始める方も、すでにニシアフと暮らしている方も、この記事がベストな給餌スタイルを見つけるヒントになれば幸いです。最後までお読みいただきありがとうございました☺