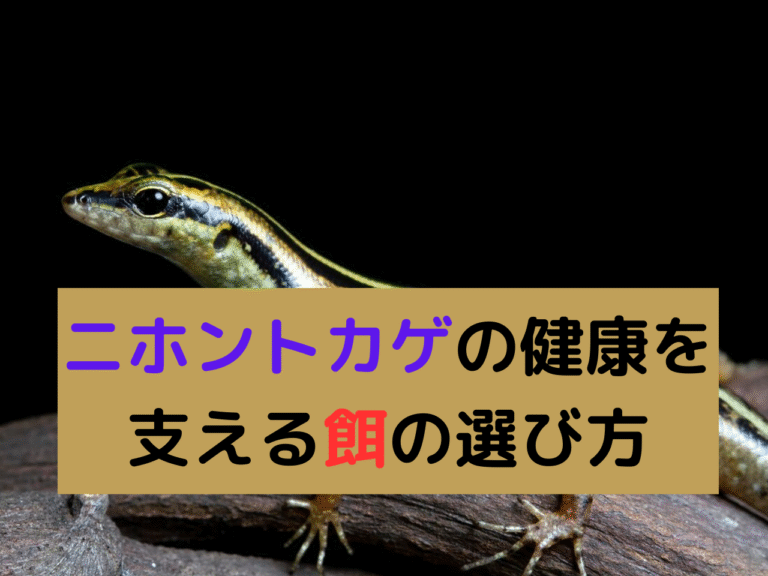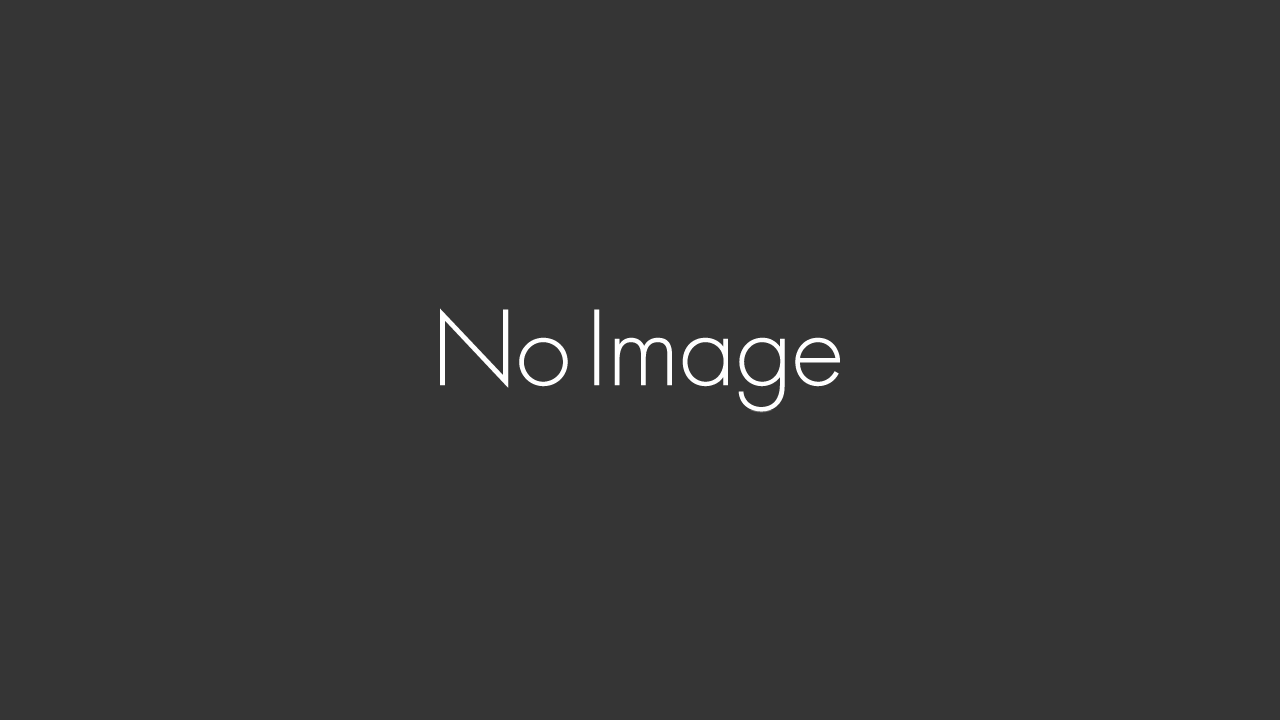ニホントカゲは、日本の自然の中でよく見かける身近な爬虫類です。幼体のときにはメタリックな青い尾を持ち、美しさと可愛らしい動きから飼育を始める人も少なくありません。
しかし、野生で自由に餌を探している二ホントカゲを飼育するとなると、どのような餌を与えれば良いのか、悩む方も多いはずです。
この記事では、ニホントカゲの食性や餌の種類、給餌の方法、季節による変化への対応まで、飼育者が押さえておくべきポイントを解説します。
ニホントカゲとは?
ニホントカゲは、日本全国に分布している在来種で、トカゲ科に分類されます。日光を好み、気温が高い日中に地面を素早く動き回りながら昆虫や小動物を捕らえて生きています。
一方、飼育下ではそのような自由な狩りはできません。飼育者が適切な餌を選び、環境に合わせて与える必要があります。自然界での生活を意識しながら餌を用意することが、健康を守るうえでとても大切です。
野生のニホントカゲが食べているものとは?
野生下のニホントカゲは、主に動いている小さな昆虫や節足動物を捕まえて食べています。特に好んで捕食するのは、バッタやクモ、コオロギ、ミミズ、ハエなどの昆虫です。
動くものに本能的に反応して狩りを行うため、飼育下でも“動き”のある餌を好む傾向があります。
ケムシや蛹などの幼虫もよく食べますが、体に合わないものを与えると消化不良やアレルギー反応を起こす場合もあるため、自然界の観察に基づいた餌選びが大切です。
飼育下で与える餌の種類とその特徴
飼育下でニホントカゲに与える餌は、できるだけ野生の食生活に近づけることが理想です。とくに動きのある昆虫類は、栄養面でも嗜好性の面でも優れています。主な餌としては、以下のようなものが挙げられます。
代表的な餌
与える餌としてまず基本となるのは、フタホシコオロギやイエコオロギです。これらは動きが活発で、食いつきも非常に良好です。
ほかに、レッドローチやミルワームも一般的ですが、ミルワームは脂肪分が多いため、与えすぎには注意が必要です。
また、保存のしやすさを考えるなら、冷凍コオロギや冷凍イナゴといった冷凍餌も活用できます。これらは衛生的で使いやすく、食いつきが悪いときはピンセットで動かしてあげると、反応を引き出すことが可能です。
給餌の頻度と量の目安
ニホントカゲは年齢や成長段階によって、必要な餌の量や頻度が異なります。成長に応じて適切に調整することが健康維持に不可欠です。
幼体の場合は消化能力がまだ未熟なため、少量ずつこまめに与えるのが基本です。1日に1〜2回、1〜2匹のコオロギを目安にします。こまめな給餌により、消化への負担を軽減しつつ、成長に必要な栄養を確保できます。
成体になると、活動量や代謝が落ち着いてくるため、2〜3日に1回の給餌でも問題ありません。一度に与える量も5分以内に食べきれる程度を意識しましょう。
幼体のうちは1日複数回の小分け給餌が理想です。成長スピードが早い時期は特に、こまめな栄養補給が重要になります
活餌・冷凍餌・人工餌の違いと選び方
ニホントカゲに与える餌は、大きく3種類に分けられます。それぞれの特徴を理解し、状況に応じて使い分けることが重要です。
まず、活餌は最も自然な形での給餌となり、トカゲの捕食本能をしっかり刺激します。しかし、管理がやや手間で、逃げ出すリスクもあるため注意が必要です。
冷凍餌は保存性と衛生面に優れており、ストックがしやすいのがメリットです。動かないため食いつきが悪いこともありますが、ピンセットで動かすなどの工夫で食べてくれることもあります。
人工餌は栄養がバランスよく配合されている点で優れています。ただし、ニホントカゲは動かないものへの反応が薄く、慣れるまでに時間がかかることもあります。
人工餌にコオロギの汁をしみ込ませると、食いつきが格段に良くなります。最初はそのような工夫が重要です
栄養バランスとカルシウム補給の重要性
ニホントカゲの主食となる昆虫には、カルシウムが不足しがちです。そのため、給餌の際にはカルシウムやビタミンD3の補給を忘れないようにしましょう。
まず基本となるのが、カルシウムパウダーのふりかけです。週に2~3回、餌に軽くまぶすことで、骨の発達や神経の働きをサポートします。
また、UVBライトの設置も重要です。体内でビタミンD3を合成し、カルシウムの吸収を助ける役割を果たします。さらに、総合ビタミンサプリを時々加えることで、偏りのない栄養補給が可能になります。
餌やりで気をつけたいポイント
給餌の際には、いくつかの注意点があります。たとえば、餌がケージ内を逃げ回るとトカゲが捕まえにくくなり、ストレスの原因になります。
小さな容器に入れて与えることで、それを防ぐことができます。また、食べ残しの放置は、衛生面で問題となるため、すぐに回収しましょう。
特に湿度が高いと、カビや腐敗の原因になります。餌のサイズにも注意し、大きすぎるものは誤飲や内臓への負担を引き起こす可能性があるため、体幅に合った大きさを選んでください。
餌を食べない時の原因と対応法
ニホントカゲが餌を急に食べなくなったときは、いくつかの原因が考えられます。まず最も多いのが温度管理の不備です。
適温は25〜30℃程度で、特に夜間に気温が下がりすぎると消化活動が落ち、食欲も低下します。また、脱皮前後は一時的に食欲が落ちることがあり、自然な現象なので無理に与える必要はありません。他にも、冷凍餌のみに偏った給餌や、ケージ内のストレスも原因になります。
どうしても食べない時は、一時的にミルワームなど嗜好性の高い餌で食欲を刺激してみましょう。ただし常用は避けるべきです
季節による食欲の変化と対処法
ニホントカゲは変温動物のため、季節の変化に大きく影響を受けます。春から夏にかけては活動的になり、食欲も旺盛になりますが、秋から冬にかけては徐々に動きが鈍くなり、餌もあまり食べなくなります。
特に冬場は無理に給餌せず、自然なリズムに合わせて食欲が戻るのを待ちましょう。冬眠させる場合は準備段階で栄養を十分に蓄えさせることがポイントです。
よくある質問とその答え
冷凍餌や人工餌の選択肢が増えたことで、ニホントカゲの給餌方法にも幅が出てきました。しかし、飼育に関してはまだまだ疑問を持つ飼育者も多いのが実情です。ここでは、ニホントカゲの餌に関する「よくある質問」とその回答を、実際の飼育現場の視点から解説します。
Q1:昆虫以外を食べますか?
基本的に昆虫食のため、野菜や果物はほとんど口にしません。与える必要もありません。
Q2:人工餌だけでも飼育できますか?
慣れれば可能ですが、活餌との併用が健康管理の面では望ましいです。
Q3:冷凍餌だけで問題ありませんか?
可能ではありますが、動かない餌に反応しない個体も多く、工夫が必要です。
ニホントカゲの飼育では、個体差や環境要因によって食性や反応も変わってきます。基本を押さえたうえで、個体の様子をよく観察しながら給餌スタイルを調整することが、長期的な健康維持につながります。
まとめ
ニホントカを健康に育てるためには、野生の食性を理解しつつ、個体の成長や体調に合わせて最適な餌を選ぶことが重要です。
動きのある餌を中心に、適切な頻度と量で与えながら、カルシウムやビタミンなどの栄養素をバランスよく補っていく必要があります。
飼育環境や季節の変化にも柔軟に対応し、観察力とちょっとした工夫を重ねることで、ニホントカゲはストレスなく元気に育ってくれるでしょう。最後までお読みいただきありがとうございました☺