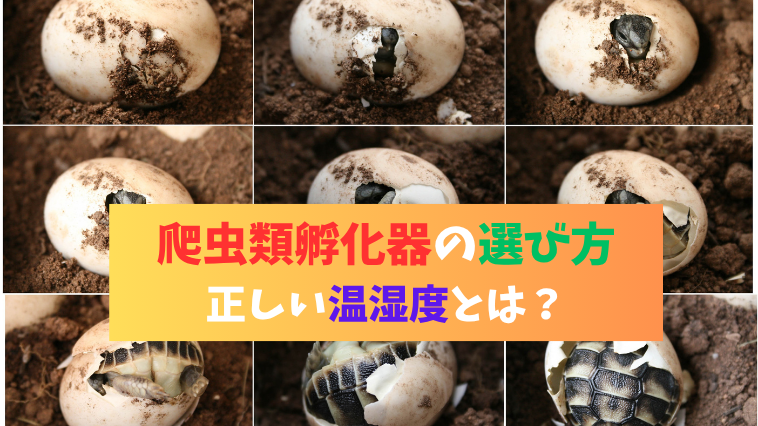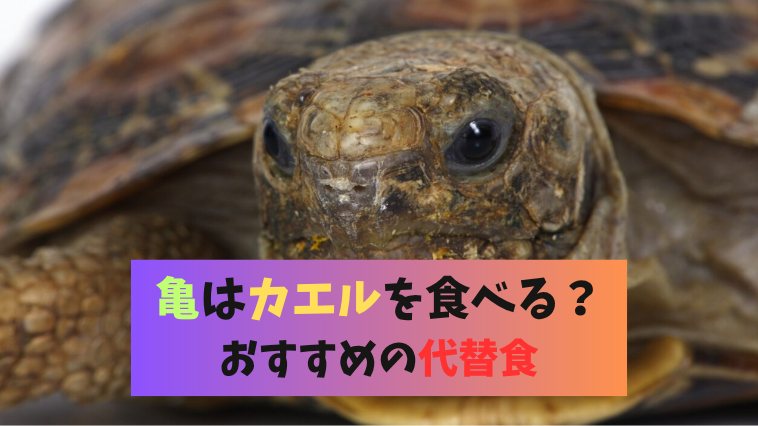ツチガエルは、日本の水辺や田んぼでよく見かける親しみ深いカエルです。飼育しやすく丈夫な性質を持っていることから、初心者でも比較的簡単に飼うことができる両生類として人気があります。
そんなツチガエルの飼育を成功させるために、最も大切なのが「正しい餌の与え方」です。餌の種類やタイミング、与える量によって健康状態が左右されるため、しっかり理解しておく必要があります。
この記事では、ツチガエルの食性の基本から具体的な餌の種類、与え方のコツ、さらには健康維持のためのポイントまで詳しく解説していきます。
ツチガエルはどんなものを食べる?

ツチガエルの健康を守るうえで、まず理解しておきたいのが「どんなものを食べて生きているのか」。これを「食性」といいます。
野生下での食事を知ることは、飼育下での餌選びのヒントになります。
ここでは自然界での主な食べ物と、家庭で再現できる食性を紹介します。
野生での食事スタイルは?
ツチガエルは、主に昆虫や節足動物などの小さな生き物を食べる肉食性の両生類です。自然界では、田んぼや小川などの水辺で暮らしながら、昆虫や節足動物を捕まえて食べています。
クモやミミズ、エビなど小型の甲殻類、地域によってはネズミなど小型の脊椎動物を補食する例も確認されています。
ツチガエルは「動くもの」に強く反応するため、自然下では活発に動く昆虫を効率よく捕まえて栄養源としています。
自宅でそろえやすい餌の種類
家庭でツチガエルを飼育する場合、自然界とまったく同じ餌を用意するのは難しいですが、近い環境を再現することは可能です。代表的なのはコオロギやミルワームなど、ツチガエルの捕食本能を刺激しやすい生き餌。
とはいえ、毎回生き餌だけを与えるのは手間がかかり、栄養も偏りやすくなります。そのため、冷凍赤虫や人工フードを組み合わせると、手軽さと栄養バランスの両立が可能です。
また、ツチガエルは季節ごとに食べるものを少し変える傾向があります。夏は昆虫類を中心に摂り、秋以降はアリなどの小型餌を好むことが多いので、飼育下でも季節に合わせて餌を変えてあげると自然な食性を再現できるでしょう。
ツチガエルにおすすめの餌
ツチガエルを健康に育てるには「何を与えるか」がとても大切です。特に初心者の方にとっては、入手のしやすさや栄養バランスも気になるポイント。
ここでは飼育でよく使われる餌の種類を、特徴や注意点とともに紹介します。
コオロギ(生き餌の定番)
ツチガエルの主食としてもっともよく利用されるのがコオロギです。生き餌として販売されているため手に入りやすく、食いつきも良いのが特徴。特に成長期には高タンパクで栄養価が高く、カルシウム補給もしやすいため理想的な餌だといえます。
幼体にはピンヘッド(1cm未満)、成体にはフタホシコオロギのMサイズ(2cm程度)が最適です。大きすぎると食べきれず、小さすぎると十分な栄養が取れないため、個体の大きさに合わせた調整が必要です。
与える前にカルシウムパウダーをまぶすことで、骨格の形成や健康維持に役立ちます。飼育初心者でも扱いやすく、ツチガエルの食性に合った定番の餌といえるでしょう。
ミミズ・冷凍赤虫(補助食)
コオロギ以外の餌としておすすめなのがミミズや冷凍赤虫です。ミミズは動きが遅く、初心者でも与えやすい餌のひとつ。栄養価が高く、特に嗜好性が高いため、食欲が落ちたときのリカバリー用にも適しています。
ただし野外で採取する場合は、農薬の影響がない場所に限るよう注意が必要です。ペットショップや釣具店で養殖個体を入手すれば安心して与えられます。
一方、冷凍赤虫は保存が利き、解凍して洗えばすぐに与えられる便利な餌です。水中飼育の個体に向いており、嗜好性も高いので冬眠明けなどに役立ちます。
ただし、赤虫ばかり与えると特定の栄養素が不足しがちになるため、主食ではなく補助食として活用するのが理想です。
カエル専用人工フード(時間がない人に)
最近では市販のカエル専用フードも販売されており、手間を減らしたい飼育者にとって心強い選択肢です。人工フードは保存性が高く、必要な栄養素がバランスよく配合されている点がメリットだといえます。
しかし、ツチガエルは動くものに強く反応する習性があるため、人工フードだけでは食いつきが悪いことも。その場合は、ピンセットで軽く動かして興味を引いたり、生き餌と交互に与えたりする工夫が必要です。
人工フードは時間がない日や出張前などに便利ですが、完全に頼り切るのではなく、生き餌や冷凍餌と組み合わせることで本来の食性に近い食事を実現できます。
バランスの良い給餌を意識すれば、人工フードはとても頼もしい補助役になりますよ!
正しい与え方と給餌のタイミング

餌の種類だけでなく、「どのくらいの頻度で、いつ与えるか」もツチガエルの健康を左右します。
成長段階や飼育環境に合わせて与え方を工夫することで、無理なく自然に近い飼育ができますよ。
成長段階に応じた頻度と量
ツチガエルは、成長段階によって必要な餌の量や頻度も異なります。たとえば、幼体の時期は体が小さく代謝も活発なため、毎日少量ずつ与えるのが基本です。特に栄養をしっかり取らせることで、丈夫な体づくりにつながります。
一方、成体になると代謝が落ち着くため、2〜3日に一度のペースで十分です。与えすぎると肥満や消化不良の原因になるので注意しましょう。
また、1回に与える量は「お腹が少しふくらむ程度」が目安。食欲が旺盛でも、消化しきれないほどの餌を与えるのは避けてください。個体によって必要量は違うため、食べ残しや排泄の状態を確認しながら調整していくのがおすすめです。
ピンセット給餌と置き餌の違い
餌を与える方法として、ピンセットを使って直接与える「ピンセット給餌」と、ケージの中に置いておく「置き餌」があります。ピンセット給餌は餌の量を把握しやすく、また飼い主とカエルの距離感を縮められる点でも人気があります。
ピンセットで軽く動かしてやると捕食本能が刺激され、人工フードや冷凍餌にも食いつきやすくなるのがメリットです。一方の置き餌は、カエルが食べ残した餌を放置することになり、不衛生になりやすいという欠点があります。
ツチガエルの健康を守るためには、なるべくピンセット給餌を基本とし、置き餌は一時的な方法にとどめるのが安心でしょう。
食べ残し対策でケージを清潔に!
ツチガエルの飼育で意外に見落とされがちなのが、食べ残しの処理。ケージ内に餌を放置すると、腐敗やカビの原因となり、ツチガエルの健康に悪影響を及ぼします。
特に水中飼育では水質の悪化につながりやすく、皮膚トラブルや病気のリスクが高まるため注意が必要です。給餌後は食べ残しを速やかに取り除き、常に清潔な環境を保つことを心がけましょう。
また、水槽で冷凍赤虫などを与える際は、水に浮かべたままにしないことが重要。ツチガエルは丈夫な両生類といわれますが、衛生管理を怠ると体調不良の原因になりかねません。
餌の与え方と同時に「後片付け」までをセットで習慣にするといいでしょう。
飼育下でも冬眠させる?冬眠前の注意点
ツチガエルは外気温が下がると活動を止め、自然に冬眠へ入る習性があります。
飼育下では必ずしも冬眠が必要ではありませんが、冬眠させる場合は環境づくりと前後のケアが欠かせません。
冬眠用の土や湿度ってどのくらい?
ツチガエルを冬眠させる際は、まず飼育ケース内に「静かな冷暗所」と「適度な湿度」を整えることが大切です。床材には腐葉土やヤシガラ土、水苔などを数センチ敷き詰め、カエルが自分で潜り込める環境を用意します。
湿度は50〜70%を保ちましょう。乾燥しすぎると脱水症状を起こすため注意が必要です。温度は5〜10℃程度が目安で、急激な温度変化は避けてください。
また、冬眠に入る前の体力が不足している個体は冬眠を乗り越えられない可能性があるため、事前に健康チェックを行うことも重要です。
元気に動けるか、痩せていないかを確認し、衰弱気味であれば冬眠は見送る方が安全だといえます。
栄養を蓄えて冬を越そう
冬眠前の食事は、冬を越せるかどうかを左右する重要な準備です。冬眠に入る2〜3週間前からは給餌頻度を少し上げ、カルシウムやビタミンを含む栄養価の高い餌を意識して与えましょう
十分な栄養を蓄えていない個体は、冬眠中に衰弱してしまう危険があります。冬眠明け直後は、内臓の働きがまだ完全に戻っていないため、すぐに大型の餌を与えるのは避けてください。
まずは嗜好性の高い冷凍赤虫など消化にやさしい餌を少量から始め、徐々にコオロギなどの生き餌に戻していくとスムーズですよ。排泄が確認できたタイミングで本格的な給餌を再開すると消化不良を防げます。
冬眠は自然なリズムですが、事前準備と明けたときのケアを徹底すると安全に乗り越えられますよ。
栄養バランスと健康維持

ツチガエルは丈夫なカエルですが、栄養が偏ると体調を崩しやすくなります。特にカルシウムやビタミンは不足しやすいため、意識的な補給と日々の健康チェックが欠かせません。
栄養のプラスひと工夫で長生きサポート
ツチガエルにとって特に不足しがちなのがカルシウムとビタミンD3。これらが欠乏すると、骨が変形したり、元気がなくなったりすることがあります。
生きた昆虫を与える場合には、カルシウムパウダーをまぶす「ダスティング」を行いましょう。週に1〜2回程度で十分です。ダスティングは、カルシウム剤だけでなく、ビタミン剤も併用することが推奨されます。
ビタミンサプリメントは週1回程度、冷凍赤虫やミミズに少量混ぜて与えると効果的です。
また、紫外線ライトを併用すれば体内でビタミンD3を合成でき、カルシウムの吸収率も高まります。こうした工夫を組み合わせることで、栄養不足を防ぎ、長く元気に飼育することが可能です。
毎日の健康チェックで元気に育てる
栄養管理とあわせて大切なのが、日々の観察による健康チェックです。ツチガエルは言葉で体調を訴えることができないため、食欲や行動の変化を飼い主が敏感に察知する必要があります。
チェックすべきポイントは、まず「餌の食いつき」です。普段より食欲が落ちていないかを確認しましょう。また、皮ふの色やツヤ、傷の有無も重要な観察項目です。特に皮ふの異常は体調不良のサインとなることが多いため注意が必要。
さらに、排泄物の状態も健康を映すバロメーターです。形や色が極端に変化していないかを観察してください。定期的に体重を測り、記録しておくことも有効で、急激な体重減少は体調不良の兆候といえます。
毎日のちょっとした観察の積み重ねが、ツチガエルの長生きにつながるのです。
餌の保存と管理方法の注意点
餌の栄養を最大限に活かすには「鮮度管理」も重要です。保存方法が不適切だと栄養価が落ちるだけでなく、カビや腐敗でツチガエルの健康を損ねる恐れがあります。
生き餌(コオロギ・ミミズ)を元気に
生きたコオロギやミミズは、購入してからもきちんと管理する必要があります。通気性のあるケースに入れ、野菜や水分を与えながら飼育しストックすると長持ちします。ただし、コオロギは過密状態にすると共食いをするため、注意が必要です。
ミミズは湿らせた土に入れて常温で保存するのが基本です。乾燥するとすぐに弱ってしまうので注意しましょう。野外で採取したものは農薬や寄生虫のリスクがあるため、必ず信頼できるショップや釣具店で入手するのがおすすめです。
冷凍赤虫や乾燥フードを正しく保存!
冷凍赤虫や乾燥フードは保存性が高く、初心者にとって便利な選択肢です。ただし、保存方法を誤ると栄養価が低下しやすいため注意が必要です。
冷凍餌は冷凍庫で保管し、使用する際は解凍後すぐに与えましょう。一度解凍したものを再冷凍すると品質が落ちるだけでなく、雑菌が繁殖する危険があります。。
乾燥餌は直射日光を避け、密閉容器に入れて保存することで劣化を防げます。湿気が多い場所ではカビの原因になるため、できるだけ風通しの良い場所に保管すると安心です。
保存状態が悪いとツチガエルの体調不良につながる可能性があるため、新鮮な状態を維持することを意識しましょう。
正しい餌選びでツチガエルと長く暮らそう

ツチガエルを元気に育てるためには、食性の理解や適切な餌を選ぶことが重要です。野生下の食生活を意識しつつ、コオロギを中心にミミズや冷凍赤虫、人工フードを組み合わせると、栄養バランスが整います。
成長段階や季節に応じて給餌方法を調整することも大切です。冬眠させる場合は事前の準備と冬眠明けのケアを徹底し、日々の観察で小さな体調変化を見逃さないようにしましょう。
さらに、餌の保存や管理を工夫すれば、常に安心して与えることができます。ツチガエルは丈夫で飼いやすい両生類ですが、ちょっとした配慮が寿命や健康に直結します。
正しい知識をもとに、ツチガエルとの豊かな暮らしを楽しみましょう。